アウトバウンド コールセンター 構築、内製と外注どっち?費用とメリットを徹底比較
- seira1001
- 2025年10月30日
- 読了時間: 21分
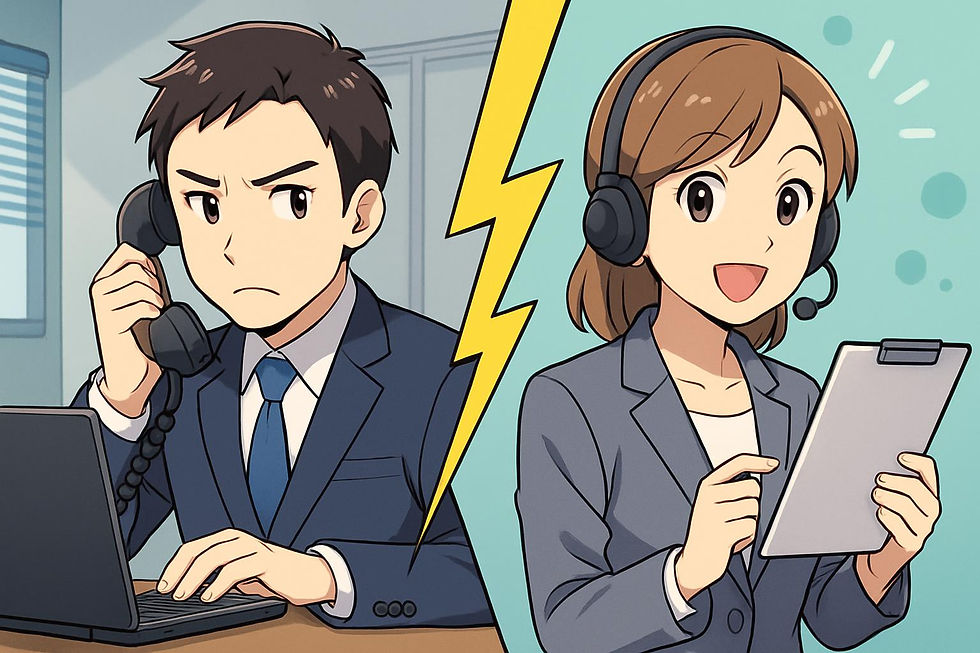
新規顧客開拓や売上向上のためにアウトバウンドコールセンターの構築を検討する際、「自社で立ち上げる内製」と「プロに任せる外注(委託)」のどちらが最適か、費用やメリットを前に悩んでいませんか?結論から言うと、長期的な視点で社内にノウハウを蓄積したいなら内製、スピーディーに専門性の高いリソースを活用し、リスクを抑えたいなら外注がおすすめです。本記事では、この判断基準をさらに深掘りし、内製と外注の費用構造、メリット・デメリットを徹底比較。それぞれの具体的な構築手順や失敗しない会社の選び方、コールセンター運営を成功させる重要ポイントまで、網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、あなたの会社の事業フェーズや目的に合わせた最適な選択が明確になり、コストを抑えつつ成果を最大化するコールセンター構築を実現できます。
1. アウトバウンドコールセンターの構築で悩んでいませんか
新規顧客の開拓や休眠顧客の掘り起こしなど、企業の成長戦略において重要な役割を担うアウトバウンドコールセンター。その重要性を認識し、自社での構築を検討しているものの、多くの課題に直面している担当者様も多いのではないでしょうか。
具体的には、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
そもそもアウトバウンドコールセンターを内製で立ち上げるべきか、専門の会社に外注(委託)すべきか、判断基準がわからない。
内製する場合の初期費用や人材採用・育成コスト、外注する場合の料金体系など、具体的な費用感がつかめず、予算計画を立てられない。
コールセンターシステムの選定や効果的なトークスクリプトの作成など、専門的なノウハウが社内にない。
オペレーターの採用や教育、モチベーション管理にまで手が回るか不安がある。
もし一つでも当てはまるなら、ご安心ください。本記事では、アウトバウンドコールセンターの構築における、こうした疑問や不安を解消します。
内製と外注、それぞれの費用やメリット・デメリットを徹底的に比較し、どのような企業がどちらの方法に向いているのかを明確に解説します。さらに、具体的な構築手順から成功のための重要ポイントまで網羅的にご紹介することで、この記事を読み終える頃には、貴社にとって最適なアウトバウンドコールセンターの構築プランを描けるようになっているはずです。
2. アウトバウンドコールセンターとは 目的と役割を解説

アウトバウンドコールセンターとは、企業側から顧客や見込み客に対して電話を発信する業務(アウトバウンドコール)を専門に行う拠点のことです。顧客からの電話を受けるインバウンドとは対照的に、能動的にアプローチする「攻め」のスタイルが特徴で、テレマーケティングやテレアポ、インサイドセールス活動の中核を担います。
単に電話をかけるだけでなく、戦略的なリスト管理や効果測定、オペレーターの育成など、成果を最大化するための多角的な運用が求められます。
2.1 インバウンドとの明確な違い
アウトバウンドとインバウンドの最も大きな違いは「電話の発信方向」です。アウトバウンドが企業から顧客へかけるのに対し、インバウンドは顧客からの電話を受け付けます。この違いにより、目的やオペレーターに求められるスキルも大きく異なります。
アウトバウンドとインバウンドの比較 | ||
比較項目 | アウトバウンドコールセンター | インバウンドコールセンター |
電話の方向性 | 企業 → 顧客(発信) | 顧客 → 企業(受信) |
主な目的 | 新規顧客開拓、販売促進、市場調査、アポイント獲得 | 問い合わせ対応、受注、テクニカルサポート、クレーム対応 |
コミュニケーションの性質 | 能動的・プッシュ型 | 受動的・プル型 |
オペレーターに求められるスキル | セールス能力、交渉力、粘り強さ、精神的な強さ | 傾聴力、共感力、正確な情報伝達能力、問題解決能力 |
2.2 主な目的は新規顧客開拓や市場調査
アウトバウンドコールセンターが担う役割は多岐にわたります。企業のビジネスモデルや戦略に応じて、以下のような目的で構築・運用されます。
2.2.1 新規顧客開拓(テレアポ)
最も代表的な目的が、見込み客リストに対して電話をかけ、商品やサービスの紹介を行い、商談のアポイントを獲得することです。BtoB、BtoCを問わず、多くの企業で営業活動の第一歩として活用されています。
2.2.2 既存顧客へのアプローチ(アップセル・クロスセル)
一度取引のあった顧客や既存顧客に対し、新商品や関連商品を案内することで、顧客単価の向上(アップセル・クロスセル)を目指します。また、長期間利用のない休眠顧客を掘り起こし、再度アクティブな顧客になってもらうためのアプローチも重要な役割です。
2.2.3 市場調査・アンケート調査
新商品の開発やサービスの改善に役立てるため、顧客満足度調査やニーズに関するアンケートを電話で実施します。顧客の生の声を直接ヒアリングできるため、質の高いマーケティングデータを得られるというメリットがあります。
2.2.4 料金や契約に関するご案内
サービスの利用料金の支払いが滞っている顧客への督促連絡や、契約更新時期が近づいた顧客への継続案内などもアウトバウンド業務の一つです。顧客との関係性を維持しつつ、確実な連絡が求められます。
3. アウトバウンドコールセンター構築 内製と外注の徹底比較

アウトバウンドコールセンターの構築を検討する際、多くの企業が直面するのが「内製」と「外注」どちらを選ぶかという問題です。それぞれに費用のかかり方やメリット・デメリットが大きく異なるため、自社の目的や状況に合わせて最適な方法を選択することが成功の鍵となります。ここでは、費用、メリット・デメリット、そして企業ごとの適性という3つの観点から、内製と外注を徹底的に比較・解説します。
3.1 費用で比較する内製と外注
コールセンター構築における最も重要な判断基準の一つが費用です。初期費用だけでなく、継続的に発生する運用費用(ランニングコスト)まで含めて総合的に比較検討しましょう。
3.1.1 内製でかかる費用の内訳
内製の場合、自社でゼロから環境を整えるため、多岐にわたる費用が発生します。特に初期投資が大きくなる傾向があります。
初期費用
システム・設備導入費:PBX(電話交換機)やCTIシステム、CRM(顧客管理システム)の導入費用、PC、ヘッドセットなどの購入費用。システムの規模やクラウド型かオンプレミス型かによって大きく変動します。
環境構築費:コールセンターを設置するオフィスの賃料や敷金・礼金、デスクや椅子などの什器購入費、インターネット回線の工事費など。
採用・教育費:オペレーターや管理者(スーパーバイザー/SV)を募集するための採用広告費や、業務開始前の研修にかかる費用。
運用費用
人件費:オペレーターやSV、管理者の給与。運用費用の中で最も大きな割合を占めます。
システム利用・保守費:クラウドシステムの月額利用料や、オンプレミスシステムの保守・メンテナンス費用。
通信費:架電数に応じた電話料金。
内製は初期にまとまったコストが必要ですが、長期的に運用すればノウハウが蓄積され、将来的にはコストコントロールがしやすくなる可能性があります。
3.1.2 外注でかかる料金体系
外注(代行会社へ委託)する場合、初期費用はほとんどかからず、主に月々の運用費用が発生します。料金体系は大きく分けて3つです。
料金体系 | 内容 | 特徴 |
成果報酬型 | アポイント獲得1件あたり、資料請求1件あたりなど、設定した成果(コンバージョン)に応じて費用が発生するプラン。 | 費用対効果が明確で無駄なコストが発生しにくいですが、成果が出なければ委託先のモチベーションが上がりにくい側面もあります。 |
固定報酬型 | オペレーターの席数(ブース数)や稼働時間に応じて、毎月固定の料金を支払うプラン。 | 毎月のコストが一定で予算管理がしやすい点がメリットです。成果の有無にかかわらず費用が発生します。 |
複合型 | 月額の固定費に加えて、成果に応じたインセンティブ(成功報酬)を支払うプラン。 | 固定費で安定した運用を確保しつつ、成果報酬で委託先のモチベーションを高めることができます。 |
外注は設備投資や人材採用のコストが不要なため、スピーディーかつ低リスクでスタートできるのが最大の魅力です。
3.2 メリットとデメリットで比較
費用だけでなく、運用面でのメリット・デメリットを理解することも重要です。自社が何を重視するのかを明確にして比較しましょう。
3.2.1 内製でコールセンターを構築するメリット・デメリット
自社で直接管理することで、ノウハウの蓄積や柔軟な対応が可能になりますが、その分リソースやマネジメントの負担が大きくなります。
項目 | 内容 |
メリット |
|
デメリット |
|
3.2.2 外注でコールセンターを構築するメリット・デメリット
専門業者に委託することで、コストやリソースの課題を解決できますが、社内にノウハウが蓄積しにくいなどの側面もあります。
項目 | 内容 |
メリット |
|
デメリット |
|
3.3 結局どっち?内製と外注が向いている企業の特徴
これまでの比較を踏まえ、自社がどちらの方法に適しているかを見極めましょう。企業のフェーズや事業戦略によって最適な選択は異なります。
3.3.1 内製での構築がおすすめの企業
顧客との対話から得られる情報を事業の資産としたい企業
長期的な視点でアウトバウンド業務を自社の強みにしたい場合や、顧客の声を商品開発やサービス改善に直接活かしたい場合に適しています。
専門性が高く複雑な商材を扱っている企業
オペレーターに高度な専門知識や深い商品理解が求められる場合、自社で直接教育する方が品質を担保しやすくなります。
厳格なセキュリティポリシーを持つ企業
個人情報や機密性の高い情報を扱うため、外部への情報持ち出しが一切許可されない場合に適しています。
3.3.2 外注での構築がおすすめの企業
すぐにでも成果を出したい、スピーディーに事業を始めたい企業
市場への早期参入を目指しており、テストマーケティングなどで迅速に結果を求めたい場合に最適です。
コールセンター運用のノウハウやリソースがない企業
人材の採用や育成、マネジメントに不安がある場合、プロに任せることで高品質な運用が実現できます。
初期投資を抑えてスモールスタートしたい企業
まずは小規模でアウトバウンド施策を試してみたい場合、低リスクで始められる外注が適しています。
自社のリソースをコア業務に集中させたい企業
アウトバウンド業務を専門家に任せ、自社の主力事業の成長に注力したい場合に効果的です。
4. アウトバウンドコールセンターを内製で構築する手順

アウトバウンドコールセンターを内製で構築する場合、行き当たりばったりで進めるのは失敗のもとです。自社にノウハウを蓄積し、長期的な資産とするためにも、計画的にステップを踏んでいくことが成功の鍵となります。ここでは、内製化を実現するための具体的な4つの手順を解説します。
4.1 ステップ1 目的とKPIの明確化
最初にすべきことは、なぜコールセンターを構築するのかという「目的」を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、成果を正しく評価できず、改善の方向性も見失ってしまいます。目的を定めたら、その達成度を測るための具体的な数値目標であるKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。
目的とKPIは、コールセンター運営の羅針盤となる最も重要な要素です。全ての戦略は、この目的とKPIに基づいて決定されます。
目的とKPI設定の例 | |
目的の例 | 対応するKPIの例 |
新規顧客獲得のためのアポイント設定 | 架電数、接触率、アポイント獲得率(CVR)、アポイント獲得単価(CPA) |
既存顧客へのアップセル・クロスセル | 架電数、受注率、顧客単価、LTV(顧客生涯価値) |
市場調査・アンケート | 架電数、アンケート完了率、有効回答数 |
休眠顧客の掘り起こし | 接触率、再アクティブ化率、コール単価(CPC) |
4.2 ステップ2 必要なシステムとツールの選定
効率的で質の高いコールセンター運営には、適切なシステムの導入が不可欠です。オペレーターの負担を軽減し、顧客情報を一元管理することで、組織全体の生産性を向上させることができます。最低限必要となるシステムと、さらなる効率化を目指すためのツールを検討しましょう。
コールセンター構築に必要な主なシステム | ||
システム種別 | 主な機能 | 導入メリット |
CTIシステム | PCと電話機能の連携、着信ポップアップ、クリックトゥコール、通話録音 | オペレーターの操作負担軽減、対応品質の均一化、トラブル防止 |
CRM/SFA | 顧客情報の一元管理、対応履歴の蓄積、営業活動の可視化 | 情報の属人化防止、顧客に合わせた最適なアプローチの実現 |
プレディクティブコール | リストへの自動発信、応答があったコールのみオペレーターに接続 | 架電効率の大幅な向上、オペレーターの待ち時間削減 |
音声認識システム | 通話内容の自動テキスト化、NGワード検知、感情分析 | 応対品質の客観的評価、コンプライアンス強化、VOC(顧客の声)分析 |
4.3 ステップ3 人材の採用と育成計画
コールセンターの品質は、システムだけでなく「人」に大きく依存します。そのため、自社の目的に合った人材を採用し、継続的に育成していくための計画が重要です。特にアウトバウンドコールは、オペレーターの精神的な負担が大きくなりがちなため、スキル面だけでなくメンタル面のケアも考慮した体制づくりが求められます。
採用においては、コミュニケーション能力やストレス耐性はもちろん、商品・サービスへの理解力がある人材が望ましいでしょう。採用後は、座学と実践を組み合わせた研修プログラムを準備します。
初期研修:商品・サービス知識、ビジネスマナー、コンプライアンス、システム操作方法
OJT:先輩オペレーターのモニタリング、ロールプレイング、スーパーバイザー(SV)によるフィードバック
継続研修:定期的なスキルアップ研修、成功事例の共有会
オペレーターのスキルとモチベーションを維持・向上させる育成体制を築くことが、コールセンターの成果に直結します。
4.4 ステップ4 効果的なトークスクリプトの作成
トークスクリプトは、オペレーターの応対品質を標準化し、成果を安定させるための設計図です。経験の浅いオペレーターでも、スクリプトに沿って話すことで一定水準の対応が可能になります。
効果的なスクリプトを作成するには、以下の要素を盛り込むことが重要です。
基本構成:挨拶からクロージングまで、会話の流れを分かりやすく構成する。
ターゲット設定:誰に(BtoB/BtoC、新規/既存)、何を伝えるのかを明確にする。
切り返しトーク集(FAQ):想定される顧客からの質問や断り文句への対応策をあらかじめ準備しておく。
共感の言葉:一方的に話すのではなく、相手の状況に寄り添う言葉を盛り込む。
最も重要なのは、スクリプトを一度作って終わりにしないことです。実際のコール結果を分析し、「どの部分で離脱が多いか」「どの言い回しが効果的か」といったデータを基に、定期的な見直しと改善(PDCAサイクル)を繰り返していく必要があります。
5. アウトバウンドコールセンターを外注する際の流れと会社の選び方

アウトバウンドコールセンターの構築を外部の専門企業に委託(アウトソーシング)する際は、信頼できるパートナー選びが成功の鍵を握ります。ここでは、外注先の選定から運用開始までの具体的な流れと、失敗しないための会社の選び方を解説します。
5.1 ステップ1 代行会社の情報収集と比較検討
まず、自社の目的を達成できる可能性のあるコールセンター代行会社を複数リストアップします。Webサイトでの検索や業界専門メディア、同業者からの紹介などを活用して情報収集を行いましょう。
候補となる会社を比較検討する際は、以下の点を確認します。
料金体系(固定報酬、成果報酬、複合型など)
過去の実績(特に自社と同じ業界や類似商材での実績)
得意分野(BtoB向けテレアポ、BtoC向けアップセル、市場調査など)
オペレーターのスキルや教育体制
セキュリティ対策(プライバシーマークやISMS認証の有無)
これらの情報をもとに、3〜5社程度に候補を絞り込み、次のステップに進みます。
5.2 ステップ2 見積もりと契約
候補の会社に問い合わせを行い、具体的な業務内容や目標(KPI)を伝えた上で、見積もりを依頼します。見積書では、初期費用、月額費用、成果報酬の条件、コール単価といった費用の内訳を詳細に確認しましょう。
契約を締結する前には、契約書の内容を隅々まで確認することが不可欠です。特に、以下の項目は必ずチェックしてください。
業務範囲とSLA(サービス品質保証)
個人情報の取り扱いに関する規定
機密保持契約(NDA)
契約期間と更新・解約の条件
不明点や懸念点があれば、担当者と十分に協議し、双方が納得した上で契約を進めましょう。
5.3 ステップ3 運用開始とレポーティング
契約後は、運用開始に向けた準備を進めます。キックオフミーティングを実施し、改めて目的やKPIを共有します。また、自社の商材やサービスに関する情報、トークスクリプトの骨子などを提供し、オペレーターへの研修を依頼します。
運用が開始されたら、定期的なレポーティングを通じて進捗を確認します。報告書では、架電数、コンタクト率、アポイント獲得率(CVR)などの主要な指標をチェックし、目標達成度を評価します。定例会などを通じて外注先と密にコミュニケーションを取り、課題の早期発見と改善サイクルの構築を目指しましょう。
5.4 失敗しない外注先の選び方3つのポイント
数ある代行会社の中から、自社に最適なパートナーを見つけるためには、いくつかの重要な視点があります。ここでは、特に重視すべき3つのポイントをご紹介します。
5.4.1 ポイント1 実績と専門性の高さ
まず確認すべきは、自社の業界や商材における実績です。BtoBの新規開拓アポイント獲得と、BtoCの既存顧客へのアップセル提案では、求められるスキルやノウハウが全く異なります。公式サイトの導入事例や顧客の声を確認し、自社の目的に合致した実績が豊富かを見極めましょう。
5.4.2 ポイント2 オペレーターの品質と教育体制
コールセンターの成果は、オペレーターの応対品質に大きく左右されます。そのため、どのような採用基準でオペレーターを集め、どのような研修制度を設けているかを確認することが重要です。品質管理体制(モニタリングやフィードバックの仕組み)が整っている会社は、高いパフォーマンスが期待できます。
5.4.3 ポイント3 堅牢なセキュリティ対策
アウトバウンドコールでは、顧客の個人情報という重要な資産を預けることになります。万が一の情報漏洩は、企業の信用を著しく損なう重大なリスクです。プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得しているかなど、客観的な指標でセキュリティレベルを確認しましょう。また、特定商取引法などのコンプライアンス遵守の姿勢も重要な選定基準です。
6. コールセンター構築を成功させる重要ポイント

アウトバウンドコールセンターの構築は、内製・外注を問わず、立ち上げて終わりではありません。成果を最大化し、継続的に運用していくためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、構築方法に関わらず成功に不可欠な3つの要素を解説します。
6.1 質の高いリストの準備
アウトバウンドコールの成果は、アプローチする「リストの質」で8割が決まると言っても過言ではありません。どれほど優れたオペレーターやトークスクリプトを用意しても、ターゲットとかけ離れたリストに架電していては、アポイント獲得や成約には繋がりません。
質の高いリストとは、自社の製品・サービスのターゲット層と合致しており、かつ情報が最新であるリストを指します。具体的には、社名、部署名、担当者名、電話番号、決裁権の有無などの情報が正確であることが求められます。リストは自社のCRMやSFAに蓄積された顧客情報のほか、リスト販売会社から購入する方法などで準備できます。どのような方法で入手するにせよ、定期的なクリーニングを行い、常に情報を最新の状態に保つことが重要です。古い情報や重複データが混在していると、架電効率が著しく低下し、オペレーターの疲弊にも繋がります。
6.2 オペレーターのモチベーション管理
アウトバウンドコールは、顧客から断られることが日常茶飯事であり、オペレーターにとって精神的な負担が大きい業務です。そのため、オペレーターのモチベーションを高く維持することは、コールセンター全体の生産性、ひいてはアポイント獲得率や成約率に直結する非常に重要な課題です。
モチベーションを管理するためには、以下のような施策が有効です。
適切な目標設定と評価制度:現実的で達成可能なKPI(重要業績評価指標)を設定し、成果を正当に評価する仕組みを整えます。成果に応じたインセンティブ制度の導入も効果的です。
定期的なフィードバック:スーパーバイザー(SV)が定期的に1on1ミーティングを行い、オペレーターの頑張りを認め、課題や悩みに寄り添う姿勢が大切です。成功事例の共有や、ポジティブな声がけも重要になります。
働きやすい環境の整備:オペレーターが心身ともに健康で働ける環境づくりは、離職率の低下にも繋がります。適度な休憩を促したり、リフレッシュできる休憩室を設けたりするなどの物理的な配慮も欠かせません。
6.3 定期的な効果測定と改善
コールセンターを成功させるには、「構築して終わり」ではなく、継続的にPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回し続けることが不可欠です。定期的に活動の成果を数値で測定し、課題を特定して改善策を実行していくプロセスが、成果の最大化に繋がります。
効果測定では、目的に応じたKPIを設定し、その数値をモニタリングします。代表的なKPIには以下のようなものがあります。
KPI項目 | 内容 |
コンタクト率 | 架電した件数のうち、実際に担当者と通話できた割合。リストの質や架電する時間帯が影響します。 |
アポイント獲得率(AP率) | コンタクトできた件数のうち、アポイント獲得に至った割合。トークスクリプトやオペレーターのスキルが影響します。 |
CPA(Cost Per Acquisition) | 1件の成果(アポイントや成約)を獲得するためにかかったコスト。費用対効果を測る重要な指標です。 |
これらの数値を分析し、「コンタクト率が低いならリストを見直す」「アポイント獲得率が伸び悩んでいるならトークスクリプトを改善する」といった具体的な改善アクションに繋げていくことが、コールセンター成功の鍵となります。
7. まとめ
本記事では、アウトバウンドコールセンターの構築方法について、内製と外注の選択肢を費用やメリット・デメリットの観点から徹底的に比較解説しました。どちらか一方が絶対的に優れているというわけではなく、自社の目的、予算、リソース、そして将来の事業戦略によって最適な選択は異なります。
結論として、アウトバウンド業務のノウハウを社内に蓄積したい、顧客情報を厳格に管理したい、長期的な視点でコストを最適化したい企業は「内製」が向いています。一方で、専門的なノウハウをすぐに活用したい、初期投資を抑えてスピーディーに立ち上げたい、社内リソースが不足しているといった企業には「外注」がおすすめです。
どちらの方法を選択するにせよ、アウトバウンドコールセンターを成功させるためには、「質の高いリストの準備」「オペレーターのモチベーション管理」「定期的な効果測定と改善」という3つのポイントが共通して重要になります。これらのポイントを疎かにすると、期待した成果を得ることは難しくなるでしょう。
この記事で解説した比較ポイントや構築手順を参考に、自社の状況を整理し、事業成長に最も貢献するアウトバウンドコールセンターの構築方法を選択してください。



コメント